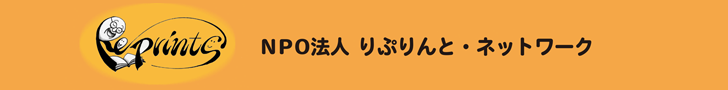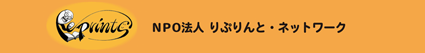新着情報&イベント
りぷりんとネットワークのトピック
新着記事

メディア掲載記事
『絵本の読み聞かせ』は、世代間の架け橋


絵本は、さまざまな喜怒哀楽の感情を物語りにのせて、子どもたちの心に届けます。また「あの頃」を懐かしむシニア世代をはじめ、多くの世代をも惹きつけます。無数にある絵本の中から、子どもに望ましい作品を選び、熟読し、音読練習を反復することは、シニア世代の高度な知的活動です。そして、地域の大人と子どもが街でつながっていた「あの頃」と絵本を架け橋にして、復元しよう、という試みが、シニアボランティアによる「絵本の読み聞かせプロジェクト」、”りぷりんと”です。
毎週1冊の絵本を読み聞かせる、そして耳を傾ける、というコミュニケーションを通して、心の栄養をお互いが分け合い、子どももシニア世代も、そしてそれを見守る世代も元気になる-それが ”りぷりんと”の願いです。
なぜ、今、世代間交流が求められるのか

少子高齢化が進む先進国では、高齢者のためだけや子育てのためだけ、といった二者択一の公共政策だけでは世代間の対立を招きかねないと言われています。その打開策としてアメリカではすでに、1990年代初頭から保健・福祉・教育分野を中心に、地域における世代間の共生・共益、つまり'Winーwin'(一石二鳥)をねらったパイロット事業が進められてきました。
わが国では核家族化、過度なプライバシー保護・匿名化の影響で人間関係が希薄化し、コミュニティの崩壊が進んでいます。一度疎遠となってしまった世代と世代をつなぐには、自然発生的で私的・個人的な交流の促進のみでは不十分であり、熟慮された「仕掛け(プログラム)」を要するとも言われています。
「りぷりんと(REPRINTS)」研究
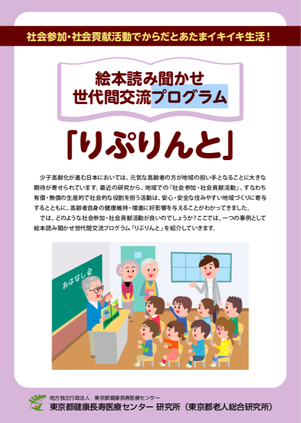
東京都老人総合研究所、社会参加とヘルスプロモーション研究チーム(現在は東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム)では、2004年度より、東京都や厚生労働省の厚生労働科学研究費補助金等の助成を受け、子どもたちへの絵本の読み聞かせを主な活動とした、シニア世代による学校支援ボランティアの養成に着手しました。
そして、シニアボランティアと子どもたちとの世代間交流が、相互にどのような影響を与え合い、双方にどのような効果をもたらすのかを調査する先駆的研究として
「世代間交流による高齢者の社会貢献に関する研究」
Research of productivity by intergenerational sympathy
を開始しました。この研究の頭文字をとって、" REPRINTS " 「りぷりんと」と命名されました。
「りぷりんと」とは文字通り「復刻版」を意味し「一度は廃刊になった名作絵本が復刻するのと同じように、シニア世代が自らの人生に再びスポットをあて、その役割を取り戻し、コミュニティの再生のために復刻を遂げてほしい」という願いも込めて命名しました。
賛助会員
(団体)エーザイ株式会社、株式会社福音館書店
(個人)6名